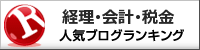こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
いよいよ明日2月1日から、令和4年分の確定申告の受付が始まります。
え!?確定申告は2月16日からでは??
と思った方もいらっしゃると思いますが、実は『還付申告』、つまり源泉徴収などで払いすぎた所得税を還付してもらう手続きや、贈与税の申告は、明日から受付可能です。
還付申告の場合、早く申告すればその分早く還付されますので、明日からどんどん申告しましょう!
また、e-taxを使った電子申告は、郵送や税務署窓口での申告よりも早く還付されます。
今年から、e-taxの機能もますます充実し、青色申告決算書や収支内訳書がスマホで作成でき、スマホ1台で完結することも可能です。
詳細は、 ↓↓こちらまで
スマホとマイナンバーカードでe-Tax!|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)